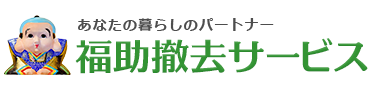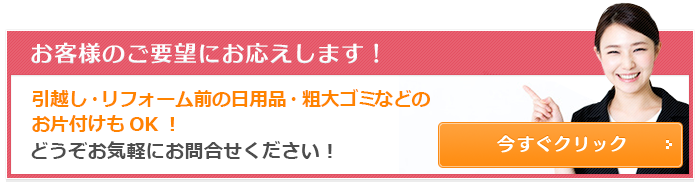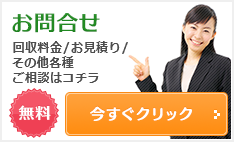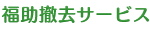下記の手順を守って、ご依頼下さい
放置自転車無料回収の手順について私有地および私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになります。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しいので、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくことと、警察に相談しながら、警察との連携で対応することで撤去の際に、手順を踏んでの対応をきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
まずは、以下のような文言を記載し警告札(告知文)を、放置と思われる怪しい自転車全てに貼りましょう。
パンクやそもそも壊れていて乗れない。
錆がひどく、ホコリが溜まっている。
鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない。
長期間乗った形跡がない。(駐輪位置が変わっていない)
(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)
上記のような文章をA4サイズの用紙に大きめの文字で3~4列ほど記入し、プリントしたものをハサミやカッターで切ると、同じ文章の書かれた紙がA4サイズ1枚から3~4枚作れ、それを自転車のハンドル部分に巻き付けてホチキス止めする方法です。
それと同時に、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
放置自転車の処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、撤去の通知を行ったら、その実施したことを、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。
各ステップにおいて、記録を残すことによって、後の不本意なクレームになった場合に、貸主(管理会社)側は、「撤去・処分」の実行にあたっては、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真をデジカメ等で撮っておくとよいでしょう。
警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の「所有者・管理者」の判断により処分することになりますが、できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行いましょう。
対応時のポイントとしては、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」です。
私有地内などにある放置自転車を敷地外(放置禁止区域、公道)へ持ち出す行為は不法投棄とみなされ、法律により罰せられることもありますのでご注意ください。
 放置自転車は、持ち主が不明だったり、盗難車などが含まれている可能性があり、不法駐輪の放置自転車であったとしても貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、いかなる場合でも法律上、勝手に処分できないことになっているので、トラブルや損害賠償のリスクを避けるため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
放置自転車は、持ち主が不明だったり、盗難車などが含まれている可能性があり、不法駐輪の放置自転車であったとしても貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、いかなる場合でも法律上、勝手に処分できないことになっているので、トラブルや損害賠償のリスクを避けるため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
放置自転車の撤去の手順管理物件のや敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間がかかり、マンションの駐輪場で深刻化している放置自転車問題は、住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる課題です。
面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいのですが、放置自転車の撤去を行う際に覚えておかないといけないのは、手順を踏んだからといって、合法的な処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえますが、下記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
STEP1:撤去予告通知の提示
警告札(告知文)を、その土地の「所有者・管理者」が放置と疑われる自転車のサドルやハンドルに取り付け、放置された自転車か、入居者が使用しているものか調査をいたします。(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)
それに併せ、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行いますが、この際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントになります。

STEP2:写真などで記録する
撤去の通知を行ったら、処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残し、万が一、後から所有者が現れ不本意なクレームになった場合は、「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで対応を行っているという証拠となり、損害賠償を請求された場合に備えて、撤去した自転車の価値判断の根拠として、必ずデジカメで撮影しておき、面倒でも1台1台、特徴の解るように撮影することをお奨めします。
記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている現場、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておくとよいでしょう。

STEP3:撤去について警察署に連絡
警告期間経過後も所有者が現れず移動しないときには、撤去の理由を明確にして、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
放置自転車が盗品の場合、警察に盗難届が提出されている可能性があり、盗難届が提出されていれば、刑事事件に関する対応の一環として、警察が放置自転車を引き取ってくれます。
そのため、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。

STEP4:放置自転車の撤去処分
警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、最寄りの警察署に相談後は、警察からの指示に従って対応を行ってください。
盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、警察と連携を取りながら放置自転車の「処分・廃棄」にあたってください。
![]() 東京都・埼玉県エリアでの自転車無料回収のことなら、福助撤去サービスにお任せください!
東京都・埼玉県エリアでの自転車無料回収のことなら、福助撤去サービスにお任せください!
駐車場の快適な駐輪スペースの確保と駐輪場の美化に貢献することを、必ずお約束いたします。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設
![]() 東京都・埼玉県での自転車無料回収のことなら、自転車無料撤去の福助撤去サービスにお任せ下さい!
東京都・埼玉県での自転車無料回収のことなら、自転車無料撤去の福助撤去サービスにお任せ下さい!